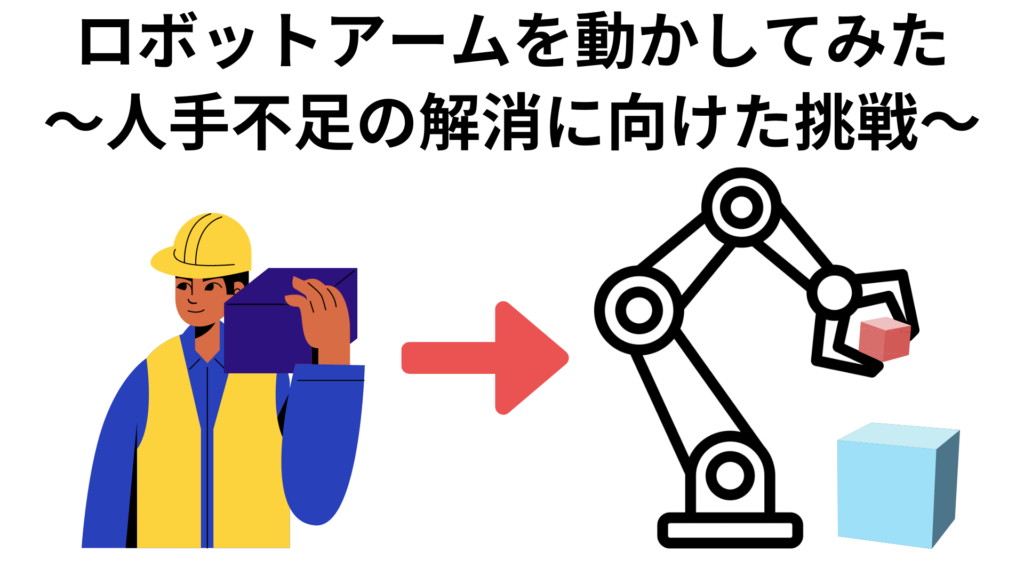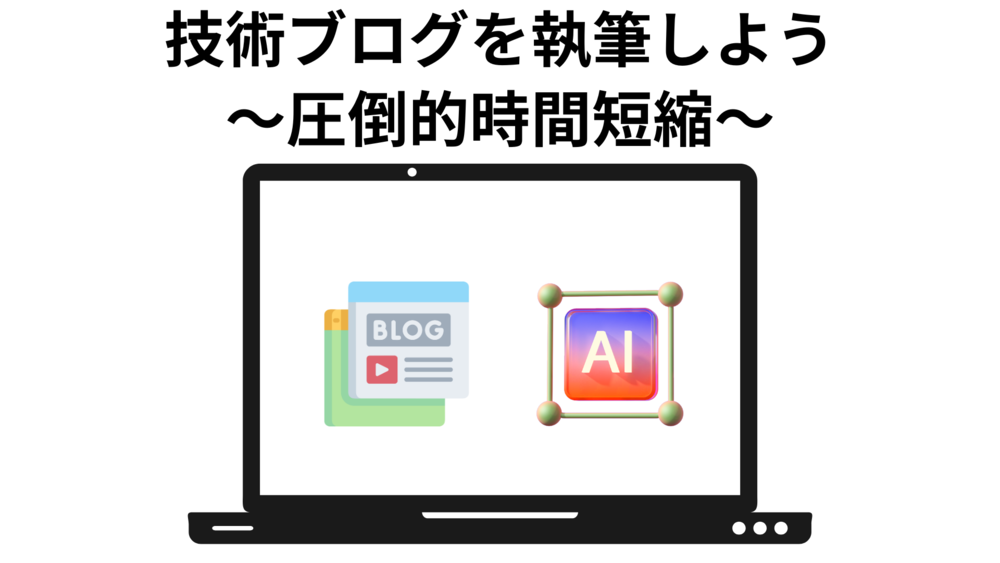SERVICEサービス
農業へのAI活用
収益悪化・後継者不足・環境問題など、農業の生産現場が抱える様々な課題に対して、AI・ドローン・IoT等の最先端ICT技術を活用した農業と地球環境に好循環を生むサービスを提供し解決へと導きます。


PROJECTプロジェクト
DX支援システム開発
製造業DXを支援するRPA開発業務、現場にフィットするシステム開発で年間数百時間以上の工数削減を実現した事例をご紹介します。課題を丁寧にヒアリングし、貴社の課題に寄り添った技術活用のご提案から実装・保守までを支援します。